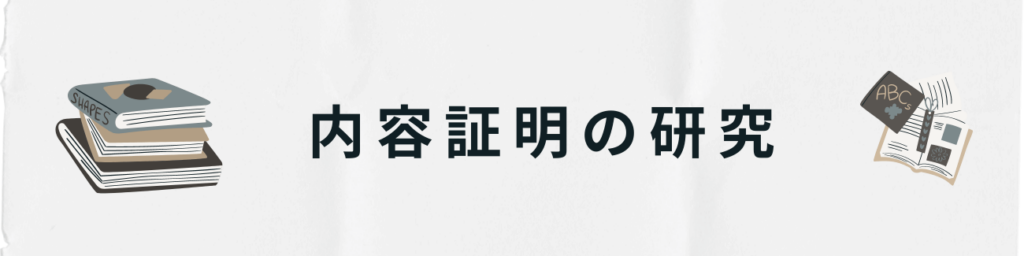内容証明郵便とは?
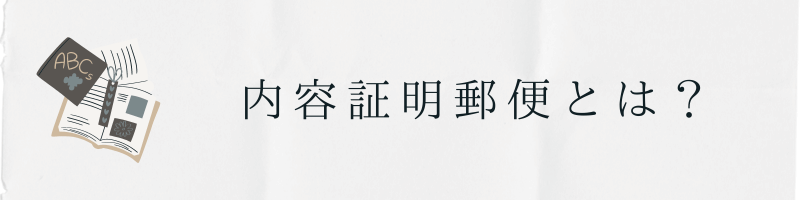
内容証明郵便は、送信された書類の内容や受け取り日時を法的に証明する郵便局のサービスです。
契約の解除を通知する際や、未払い代金の督促などで利用されることが多いのですが、普通郵便とはいったい何が異なっているのでしょうか。
内容証明郵便の制度や、どのように書くのか、また出すときの注意点等を利用前に知っておくことは大切です。
内容証明郵便は、訴訟になった場合には有効な証拠となります。内容証明郵便のメリットや正しい利用方法を把握しておきましょう。
内容証明の支払いにはクレジットカードの利用が可能です。
内容証明郵便のメリット3つ
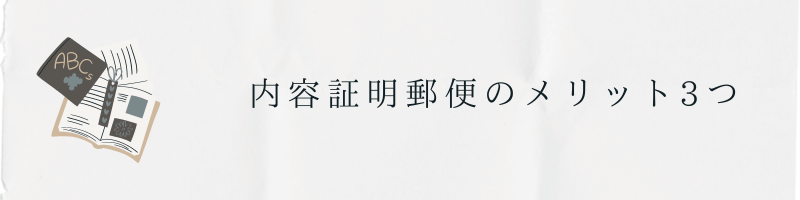
内容証明郵便を利用するメリットには、どんなものがあるのでしょうか。
信頼性が高まる
内容証明郵便の利点はまず、送信された書類や物品の内容や受け取り日時が法的に証明されるため、信頼性が高まる点があげられます。
法的な裏付けがあるため、通知や契約の際に紛争を防げるでしょう。
また、書類の内容や受け取り日時の証明が後で必要になった場合、内容証明郵便を利用しておけば手軽に入手できます。
心理的圧迫を与えられる
内容証明郵便は、受け取った側に訴訟の前段階であるとわからせ、心理的な圧迫を与えます。
差出人が強い意志を持っていると伝えらえ、内容に関する強制的な効果も期待できるでしょう。
これまでメールや電話では解決できなかった、無視されてしまっていたケースでも、内容証明郵便なら確実に相手に影響を与えられます。
受け取りをごまかせない
普通郵便と違って内容証明郵便なら、届いていなかった、受け取っていないとはごまかせません。
差出人と郵便局に証拠が残っているので、証拠隠滅や放置、そのまま逃げるといったことはできなくなるのです。
内容証明郵便のデメリット4つ
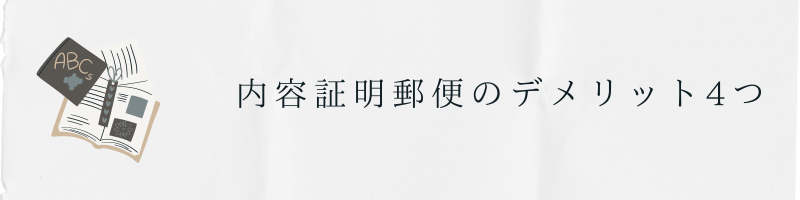
内容証明郵便には、メリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。
撤回ややり直しはできない
内容証明郵便を送ると、これまでの相手との関係性をがらりと変えてしまう可能性があります。
送ったことにより相手がどう受け止めるかは予測できない部分もあるため、さらにトラブルが大きくなったり、解決が遠のいたりするケースも起こり得ます。
送った内容の撤回や、一度送ったものを取り戻してまたやり直すといったこともできません。利用する際には十分な注意が必要でしょう。
内容によって罪に問われる可能性も0ではない
内容証明郵便の内容が、受け取った側に譲歩や妥協を許さないと、脅迫や恐喝になりかねません。
時間的猶予を持たせておいたり、書面での回答を待ったりなど、相手の行動を促せる内容にしておかないと、恐喝罪や脅迫罪に問われる可能性が出てしまいます。
相手方に有利な証拠となることがある
内容証明郵便の内容を吟味してから送らないと、相手に有利な情報を与える結果になります。
相手の対応を求めるあまりに、知られたくないこと、伝わると最終的に自分に不利になることも文面に入れ込んでしまうケースがあります。
文面の作成には要点をきちんと押さえ、内容を慎重に検討してから送りましょう。
郵送や作成の費用や日数に注意する必要あり
内容証明の書類作成を、専門家に依頼すると費用がかかります。
弁護士なら3万円、司法書士なら2万円程度が相場といわれています。
また内容証明郵便として送る際には、一般書留の加算料金と内容証明の加算料金が基本料金に加わるため送る側にとっては、負担となる場合があります。
また、郵送には、1週間程度かかりますので急ぎの通知や契約には向いていないことがあります。
内容証明の郵便料金は基本料金に加算
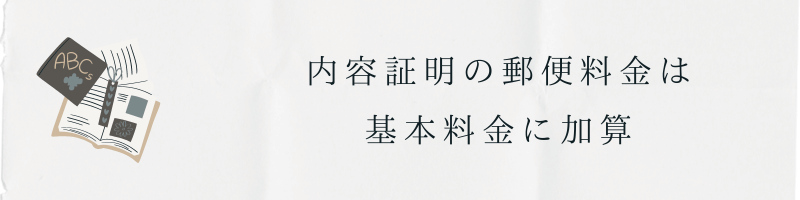
内容証明郵便の料金は、郵便の基本料金に加算されます。
内容証明郵便は一般書留の扱いとなるため、基本料金に一般書留料金と内容証明料金がプラスされますのでご注意ください。
内容証明の加算料金は480円(枚数が2枚以上なら2枚目以降は290円増)、一般書留の加算料金は480円です。
A4書類一枚を内容証明郵便として送りたい場合には、下記の料金になります。
84円(25gまでの定型郵便物料金)+480円(一般書留加算料金)+480円(内容証明加算料金)=1,044円
内容証明謄本を紛失するとどうなる?
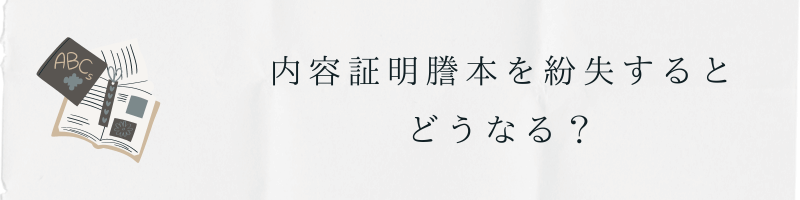
内容証明郵便は、送付する書類と謄本(写し)を2枚準備し、謄本の一枚は送り主、もう一枚は郵便局が保管するきまりです。
万が一、自分が保管している内容証明謄本が紛失した場合には、再交付を受けられます。
裁判などでは証拠物となるため、謄本を必要とするなら内容証明郵便を送った郵便局で再交付(再証明)をしておきましょう。
再発行手続きには時間がかかる場合があるため、保管方法や保管場所には注意しましょう。
内容証明郵便の書き方のポイント
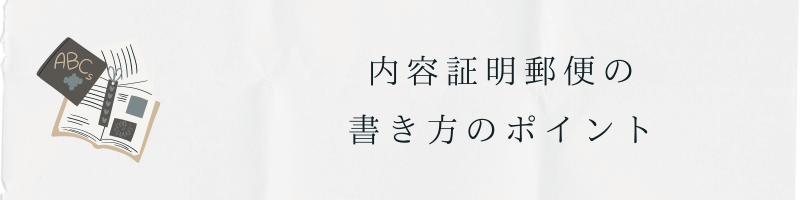
内容証明郵便を送る際の基本的な手順やポイントを以下にまとめました。
用紙は自由に選べる
内容証明の用紙は、自由に選べて特に制限はありません。また、用紙枚数にも制限はないですが、2枚以上にわたる際はつづり目に契印が必要になります。
どんな用紙を使ってもよいのですが、字数と行数に制限があります。
・用紙を横書きで使用する場合
1行26字以内で、用紙1枚には20行以内。または1行13字以内で、用紙1枚に40行以内。
・用紙を縦書きで使用する場合
1行20字以内で、用紙1枚26行以内
1枚の用紙に内容が収まらなければ、枚数を増やして作成しましょう。
内容証明で記載すること
内容証明の記載内容には下記のものがあります。
- 文書の表題
- 通知内容
- 日付
- 相手の住所、氏名(法人なら社名と代表取締役氏名)
- 自分の住所、氏名(法人なら社名と代表取締役氏名)
書面作成では、上記の順に記載するのが一般的です。
内容証明の契印・押印はどこに必要?
内容証明書類には、押印は必須ではなく差出人の任意です。
ただし、謄本の内容を訂正するときの訂正印と、謄本の枚数が2枚以上にわたるときの契印は必要になります。
契印は、2枚以上に用紙がなったらホッチキス等でとじて、ページとページの間に割印します。割印に使用するのは、差出人氏名の横に押印した印鑑と同じものです。
使用する印鑑は実印でなくてもよく、普段使用しているもので問題ありません。シャチハタの使用は避けましょう。
内容証明の表題は必須ではない
内容証明には表題(タイトル)をつけてもつけなくても問題はありません。
とはいっても付けるケースが多く「催告書」「通知書」「請求書」「通告書」などがよく見られます。
さらに具体的に「家賃値上通知書」や「賃金請求書」と記載しているものもあります。
要は内容証明の文面の具体的な内容を簡潔に既述することが重要です。受取人が表題だけで文面の内容を予測でき、わかるように付けましょう。
通知内容は明瞭に書く
内容証明の通知内容、いわゆる本文は分かりやすく簡潔に書きましょう。
通常の手紙のように時候の挨拶や、終わりの挨拶を使うケースはほとんどありません。
挨拶文を入れるのは、受取人に悪感情を抱かせたくない、関係の変化をもたらしたくない、商業文のような形式をとりたいときです。その場合は、表題を入れずに内容証明の文章を作成します。
本文をどのように書くのかは、内容証明の目的により異なりますが、具体的な事項や日時などをきちんと入れるようにしましょう。
以上が内容証明郵便を送る際の基本的な書き方です。
専門家に依頼する方法もありますが、サンプルの文面も検索すれば見つかりますので、それに倣って自分で作成するのも一つの方法です。
債権譲渡した場合の内容証明書類の文例
「当法人は、当法人が貴殿に対して有する以下の債券を、×年
×月×日付で、株式会社△△△△(本社所在地:□□、代表取
締役:□□□□、連絡先:○○-○○○○-○○○○)に譲渡しましたの
で通知します。
今後の弁済は、株式会社△△△△宛に行っていただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。
記
債券の種類:□□□□
債券の発生日:×年×月×日
金額:○○○○円
以上」
内容証明郵便の出し方の流れ
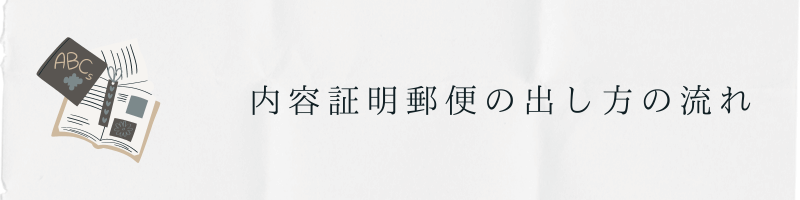
内容証明郵便を送る方法について、以下に詳しく説明します。
内容証明郵便の出し方の手順に従って準備しましょう。
内容証明郵便を出す時の流れ
- 内容証明郵便の書類を3部準備する。
- 3部全て氏名の横に押印する。(法人なら法人印を社名の横に押印)
- 内容証明の書類枚数が2枚以上のときは、ホッチキス等で止めて割印
- 封筒に相手の住所、氏名(社名)と自分の住所、氏名(社名)を書く
- 郵便局に持参して発送
- 控えを保管
書類を3部作成するのは、発送用、郵便局控え用、差出人控え用が必要なためです。書類すべてに押印しましょう。
郵便局によって、内容証明郵便を取り扱っていないことがあるので、事前に確認が必要です。
郵便局のWebサイト
https://map.japanpost.jp/p/search/?&cond200=1&
「郵便サービスから選ぶ」の項目に「内容証明」があるので、チェックを入れて検索しましょう。
郵便局で配達証明を付けるかどうか確認されることがありますが、相手の受け取りがわかるために必要ですから確認の有無にかかわらず、必ず配達証明をつけるようにします。
配達証明は350円かかりますが、差出後に配達証明を請求すると480円必要です。先につけておくほうがよいでしょう。
電子内容証明で出す方法もあり
電子内容証明(e内容証明)というサービスも郵便局では取り扱っています。
e内容証明は、24時間いつでも内容証明郵便を発送できるサービスです。
使い方は、Wordファイルで内容証明文書を作成し、インターネット上にアップロードするだけです。
アップロードすれば、郵便局の機械で印刷、照合、封入・封かんを行い内容証明郵便として受取人宛に発送してくれます。
文字数が多い場合や、発送通数が多い場合などは通常の内容証明郵便より料金が安くなります。またオンラインでいつでも手続きできるので、時間や手間をカットできます。
たとえば、書面で内容証明文書を送る場合に1,500文字だと3枚にわたり、料金は1,624円かかります。e内容証明なら1枚ですみますので1,265円と359円お得です。
書類を持ち出さなくてよいのでセキュリティ面でも安心感があります。
ただし、e内容証明郵便の登録の必要があること、支払い方法は原則クレジットカードのみ、専門家に依頼しても弁護士等の専門家の職印を押せない点には注意が必要です。
内容証明郵便はどんなときに出す?
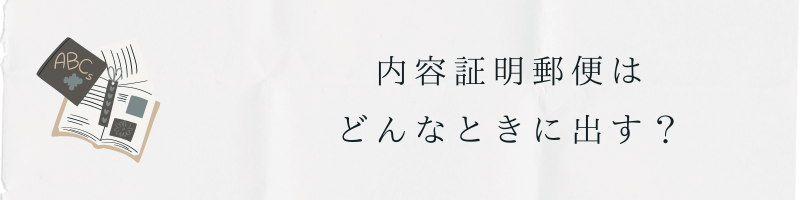
内容証明郵便を送るべきタイミングやシチュエーションについて、以下で解説します。
内容証明郵便を送るかどうか迷っている、こんなケースで送ってもよいのかと、気になっている場合に参考にしてください。
通知することに意味がある場合
特定の情報や通知を相手に伝える必要がある場合、内容証明郵便を利用することで、送信日時や内容を法的に証明できます。相手に確実に情報を伝えたいとき、齟齬があっては困るときに有効な方法です。
友好関係を壊したくないときは?
友人や知人に特定の情報を伝えたい場合にも、内容証明郵便を利用できます。相手に対して真摯な姿勢を示せるケースも多いのですが、利用には注意も必要です。
内容証明郵便というだけで一定の圧迫感を受け取った側に与えることが多いため、有効な関係を壊したくないなら文面には十分に気を付けて作成しましょう。
言った言わないの水掛け論を防止したいとき
口頭での約束や取り決めに不安がある場合、内容証明郵便を送ることで、書面による証拠を残すことができます。付き合いが長い場合などはどうしても曖昧になりやすい場合も、後々のトラブルを防ぐことができます。
証拠がないときに、証拠として使える
証拠が不十分な場合には、内容証明郵便を活用して証拠とする方法も取れます。
書面による証拠があるので、トラブルの解決がスムーズになることがあります。ただし、相手との関係性により書類を送った事自体がトラブルになる可能性もゼロではありません。
内容証明郵便をどんなときに出すかの判断は、個人間では難しいこともあるでしょう。悩んでいる場合には、弁護士や司法書士の専門家にアドバイスを求める方法もあります。
内容証明郵便が届かないときは?
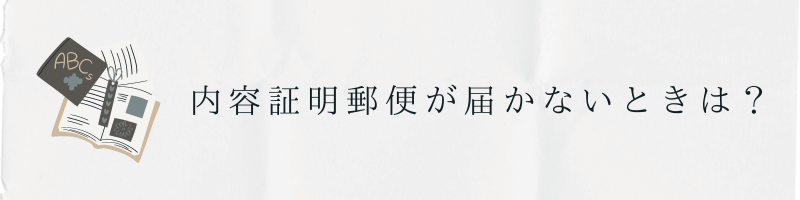
内容証明郵便が届かない場合、様々な要因が考えられます。受取人が不在である可能性や、住所不明、受取拒否等が主な理由としてあげられます。
配達証明をつけておくと、内容証明郵便が届かない場合の理由がわかります。内容証明が届かなかったいくつかのケースでの対策を解説していきます。
内容証明郵便の受取拒否の場合
受取人が内容証明郵便を受け取りたくない場合、受取拒否をすることができます。
差出人側にすると、受取拒否されればどうすればよいのかと困ってしまうかもしれませんが、実は証拠としては有効です。
受取拒否は受取人の意志で受け取らなかったので、内容証明郵便を送った差出人の意志表示は届いたとみなされます。
裁判の判例では受取拒否でも通知は行ったという意味に解釈されるため、内容証明に受取拒否がついているものも証拠になるのです。
受取人が不在だった場合
内容証明郵便は書留郵便でもあるので、不在の場合は配達員は持ち帰り郵便局で7日間保管されます。
7日間経過して受取人が郵便局へ内容証明郵便を取りに来なければ、差出人に戻ってしまいます。
不在で受取不可だった場合には、内容証明の通知が相手に届いたことにはなりません。
受取人が不在で、内容証明の通知が相手に届いていない事態を防ぐために、内容証明と同じ内容の普通郵便を特定記録で再送付します。
普通郵便なら、不在であってもポストに投函されるので、必ず配達されたことになるのです。特定記録は追跡バーコードをつけるので、送付や到達のタイミングの記録も残ります。
ただし、特定記録を伴った普通郵便の送付は、内容証明としての効力はありません。不在の際の手段として考えておきましょう。
配達されないなら、証人になってくれる人と一緒に「直接持参する」方法があります。
また、公示送達といって、裁判所の掲示場に送達したい文書を掲示し、官報や新聞に掲示したと掲載する手続きもあります。公示送達だと、一定期間経過後は、相手に書面(の内容)が到達したと見なされ、不在や居住不明でも利用できます。
内容証明郵便が送られてきたらどうすればいい?
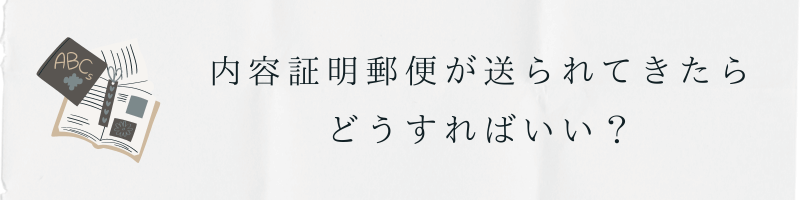
内容証明郵便を受け取った側になると、どうすればよいのか困ってしまうかもしれません。裁判や法的措置を前提として内容証明郵便を送ることも多いため、届いた際には困ってしまう可能性もありますね。内容証明が届いた場合の対策をご紹介します。
受取拒否をするとどうなるのか
内容証明の受取拒否は形式上は可能です。ただし、受取拒否をすると「受取拒否した」という記録は残ります。
受取拒否は不在と異なり、「書類は到達したが受け取っていない」という情報を差出人に伝えるので、効果はあるとみなされるのです。
その後の交渉等の対応を考えても受け取って、内容を確認してから対策を講じるほうがよいでしょう。
返事は必ず書かないといけない?
内容証明郵便に対して返事をする必要性はありません。返信の義務はないのですが、返信するならどんな内容にするかしっかり考える必要があります。
内容証明に回答すれば、受取人の認識を示す証拠資料となるので、返信するとしても内容は十分に検討しないといけません。
内容証明に法的な強制力はない
内容証明郵便には法的な強制力はありませんが、書面としての証拠価値があります。法的トラブル解決の際には、この書面が有益な情報として活用されることがあります。
内容証明が届いた段階で、驚いたりショックを受けたりして間違った対応や交渉をスタートしてしまう方もいます。
その後専門家に相談したとしても、差出人に決定的な証拠を提供したり、自分にとって不利な状況を作り出してしまったりした状態かもしれません。
書面を受け取り次第、専門家への相談を考慮したほうがよいケースもあります。